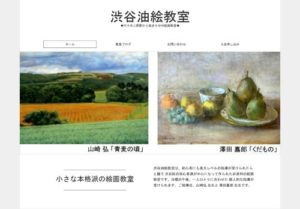-
最新ブログ
- ■売上・利益を拡大したい営業所長の話:業務マニュアル化について 2024-04-18
- ■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第3回 2024-04-17
- ■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第2回 2024-04-16
- ■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第1回 2024-04-12
- ■主語概念の混乱:森山卓郎『日本語の<書き>方』から 2024-04-11
「日本語」カテゴリーアーカイブ
■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第3回
1 文節概念の問題点 北原保雄『日本語の文法』の章立ては、3章以下 … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第3回 はコメントを受け付けていません
■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第2回
1 「文とは何か」 北原保雄『日本語の文法』第二章は「文とは何か-文 … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第2回 はコメントを受け付けていません
■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第1回
1 20世紀末の代表的な日本語文法書 「日本語の世界」という16巻から … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第1回 はコメントを受け付けていません
■主語概念の混乱:森山卓郎『日本語の<書き>方』から
1 「全国学習状況調査・中学校」での出題 森山卓郎は『日本語の<書き … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■主語概念の混乱:森山卓郎『日本語の<書き>方』から はコメントを受け付けていません
■日本語文法の課題:1981年の大野晋と丸谷才一の対談から
1 英文法を利用して国文法を考える 『日本語の世界』第6巻の付録に大 … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■日本語文法の課題:1981年の大野晋と丸谷才一の対談から はコメントを受け付けていません
■専門書の翻訳が日本語を論理的で明快・正確にした:川島武宜『ある法学者の軌跡』から
1 日本語の構造の不備 日本語の文章をチェックする講座と、日本語の読 … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■専門書の翻訳が日本語を論理的で明快・正確にした:川島武宜『ある法学者の軌跡』から はコメントを受け付けていません
■日本語の言葉についての判別方法:三上章『現代語法序説』を参考に
1 接尾辞「サ」で形容詞を判別 三上章の『現代語法序説』はもはや歴史 … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■日本語の言葉についての判別方法:三上章『現代語法序説』を参考に はコメントを受け付けていません
■言葉を対・セットの発想で考える:小松英雄『日本語はなぜ変化するか』から
1 やっかいな品詞分解 品詞分解というものを、かつては国語の時間 … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■言葉を対・セットの発想で考える:小松英雄『日本語はなぜ変化するか』から はコメントを受け付けていません
■現代語になって一番変わった文章構造:係り結びについて
1 古典文法の変容 現代語以前の日本語の文章で、いまと一番大きく違う … 続きを読む
カテゴリー: 日本語
■現代語になって一番変わった文章構造:係り結びについて はコメントを受け付けていません