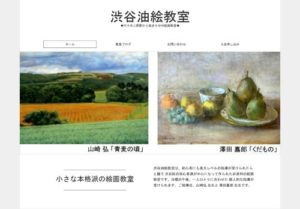-
最新ブログ
- ■梅棹忠夫「文明の生態史観」の発想:機能論的アプローチ 2024-04-19
- ■売上・利益を拡大したい営業所長の話:業務マニュアル化について 2024-04-18
- ■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第3回 2024-04-17
- ■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第2回 2024-04-16
- ■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第1回 2024-04-12
Category Archives: マネジメント
■基本原則を作るときのお手本:ヘルムート・マウハー『マネジメント・バイブル』
1 ネスレを世界的企業にしたヘルムート・マウハー ネスレを世界的 … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■基本原則を作るときのお手本:ヘルムート・マウハー『マネジメント・バイブル』
■ユニクロ柳井正の経営論のエッセンス:『プロフェッショナルマネジャー』の解説から
1 柳井正の「最高の教科書」 ハロルド・ジェニーンの『プロフェッショ … Continue reading
■成果を測る基本:顧客と利益
1 顧客と利益 マネジメントというのは、成果を上げるためのものです … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■成果を測る基本:顧客と利益
■「ビジョン」とはどういうものか:セコム創業者飯田亮の考え方
1 「経営理念」と「ビジョン」 ビジョンという言葉がビジネスでは使 … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■「ビジョン」とはどういうものか:セコム創業者飯田亮の考え方
■要素の細分化と「見える化」
1 問題の要因発見に有効な細分化 物事を分析するときに、要素を細分化して … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■要素の細分化と「見える化」
■類推・アナロジーの利用:マネジメントを考えるアプローチ
1 マネジメントの勉強 少し前から、マネジメントの勉強をする人が何 … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■類推・アナロジーの利用:マネジメントを考えるアプローチ
■アップルに関する本で一番のおすすめ:『ジョナサン・アイブ』
1 アップルの成功事例 多くの本や記事でアップルの成功事例が取り上 … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■アップルに関する本で一番のおすすめ:『ジョナサン・アイブ』
■マネジメントのエッセンス:示唆に富む「はじめて読むドラッカー」シリーズの題名
1 「はじめて読むドラッカー」シリーズ ずいぶん前に教え子たちに話し … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■マネジメントのエッセンス:示唆に富む「はじめて読むドラッカー」シリーズの題名
■ビジネスで大切なのは演繹よりも帰納的なアプローチ:業務の記述が基礎
1 演繹的なアプローチは特別な方法 ある理論をそのまま受け入れて、 … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■ビジネスで大切なのは演繹よりも帰納的なアプローチ:業務の記述が基礎
■西堀栄三郎の創造性開発:目的と制約
1 目的は絶対 西堀栄三郎は『石橋を叩けば渡れない』で、目的と制約 … Continue reading
Posted in マネジメント
Comments Off on ■西堀栄三郎の創造性開発:目的と制約