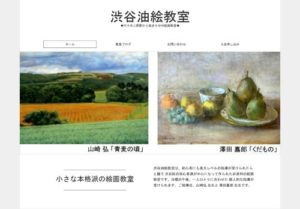-
最新ブログ
- ■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第5回 2024-04-25
- ■『日本語の世界 第6巻 日本語の文法』を読む 第4回 2024-04-24
- ■企画を立てるプロがしてきた基礎の勉強 2024-04-23
- ■梅棹忠夫「文明の生態史観」の発想:機能論的アプローチ 2024-04-19
- ■売上・利益を拡大したい営業所長の話:業務マニュアル化について 2024-04-18
Monthly Archives: 6月 2021
■オンライン講義について:その弱点と今後
1 情報量の問題 新形コロナの緊急事態宣言により、6月の業務マニュアル … Continue reading
Posted in 一般教養
Comments Off on ■オンライン講義について:その弱点と今後
■梅棹忠夫の見解について:桑原武夫『文章作法』から
1 ああそうなんですか…で終わる話 日本語に主語がないという見解が示 … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■梅棹忠夫の見解について:桑原武夫『文章作法』から
■大野晋『日本語はいかにして成立したか』にみえる基本発想
1 厳密で精確な表現の可能性 いささか困ったことになりまして、ブログの … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■大野晋『日本語はいかにして成立したか』にみえる基本発想
■日本語の体系を考える:『日本列島の言語』の亀井孝の論考から
1 近代における漢語の役割 『日本列島の言語』に収められた「日本語の歴 … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■日本語の体系を考える:『日本列島の言語』の亀井孝の論考から
■日本語の体系を考える:『日本列島の言語』の小松英雄論考から
1 機能的な記述を可能にした記述法 『日本列島の言語』にまとめられた記述 … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■日本語の体系を考える:『日本列島の言語』の小松英雄論考から
■漢文における品詞概念:形式・働き・意味による決定
1 漢字における広い意味での品詞 春という言葉は、日本語では名詞です。 … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■漢文における品詞概念:形式・働き・意味による決定
■品詞の決定要因:主語・述語概念と品詞
1 形式的な判別が可能な動詞・形容詞 日本語の文法を考えるとき、私た … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■品詞の決定要因:主語・述語概念と品詞
■名詞とは何か:主格にならない名詞について
1 大野晋による名詞の定義 名詞のことを考えていたら、そういえば大野晋 … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■名詞とは何か:主格にならない名詞について
■日本語の品詞:広すぎる名詞の概念
1 文節は区切りの単位 自立語というのは、文節で区切った先頭に来る言 … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■日本語の品詞:広すぎる名詞の概念
■日本語の品詞:明確な基準で判別可能な「形容詞・動詞」
1 「数式を組み立てる」とは 私たちが日本語で客観的で論理的な文章 … Continue reading
Posted in 日本語
Comments Off on ■日本語の品詞:明確な基準で判別可能な「形容詞・動詞」